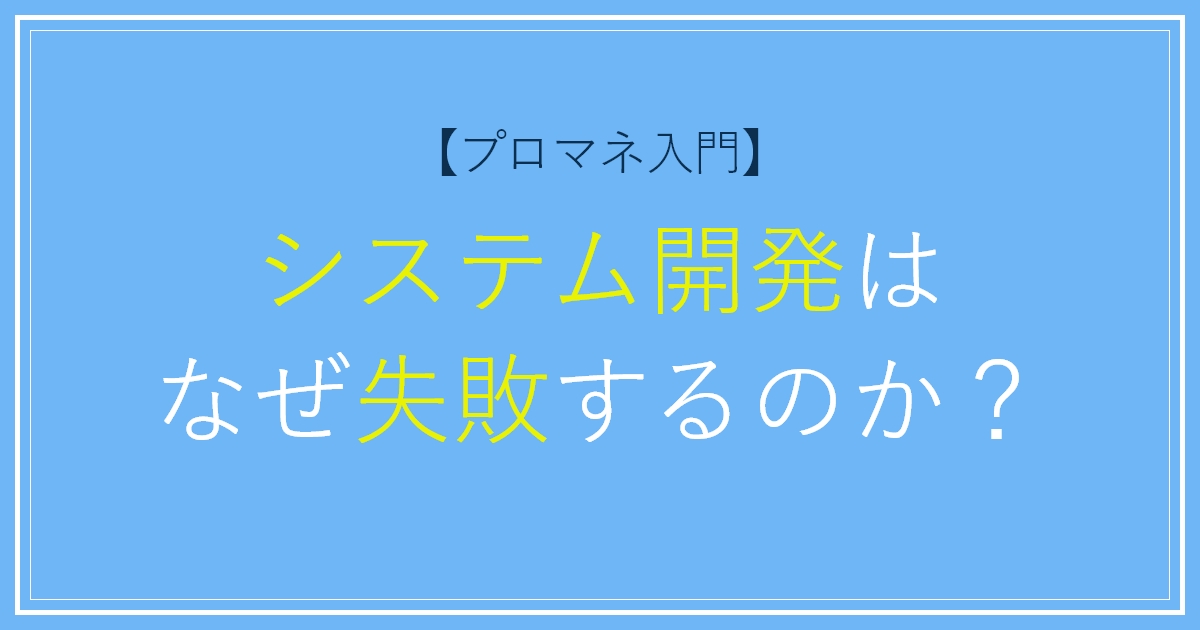急な仕様変更にクライアントの無茶ぶり。
システム開発には突発的なトラブルがつきものですが、そのような大きなトラブルがないプロジェクトでも開発が失敗することがあります。
十分余裕を持ってスケジュールを引いたはずなのに、どんどん開発が遅れていく。。
そんな経験はないでしょうか?
その原因は「損失回避性」という人間心理が関係しています。
この記事では、プロジェクト管理において知っておくべき人間心理について解説します。
人間は損することが大嫌いな生き物である

プロジェクトの失敗原因はさまざまですが、その根幹部分には「人間は損することが大嫌いである」という心理が働いていることがほとんどです。
例えばチームメンバーから「開発が遅れている」という報告を受けたとき、リーダーはどうするべきでしょうか?
- 難易度の高い部分の開発が終わればスピードが上がるはずだから、大丈夫だろう
- 後半になれば○○さん(ベテランメンバー)の手が空いてくるはずなので、フォローに回ってもらえるだろう
- 新人メンバーを前半厚くフォローしてあげれば、後半は一人でも大丈夫だろう
- ○○さん(ベテランメンバー)が作った機能は信頼できるから、テスト項目を減らしても大丈夫だろう(テスト期間を短くして挽回しよう)
このような考えで様子見している場合は要注意です。
「進捗遅れ」という目に見える損失が発生しているにも関わらず、それを認めたくなくて都合の良い判断をしている状態です。
このように損や失敗を認めたくないために、希望的観測でものごとを解釈することを「損失回避性」と呼びます。
なぜ損失回避の思考がNGなのか?
なぜ損失回避性思考は良くないのでしょうか?
理由は簡単で、その通りにいく確率がものすごく低いからです。
そもそも計画時点の読みがはずれて進捗遅れが発生するわけですから、その後の読みがあたるなんてことはありえないのです。
損失回避思考は必ずしも「悪」ではない

誤解しないでいただきたいのですが、損失回避は必ずしも悪いわけではありません。
例えばこの心理はマーケティングに応用できます。
マーケティングの応用例
- 期間限定セール、無料キャンペーン
「今申し込まないと高くなる(損をする)」という心理をついたもの - 返金保証
「買っても損をしない」という損失回避の安心感
あくまで「プロジェクト管理では損失回避思考が合わない」という点をご理解ください。
損失回避思考をやめればプロジェクトはうまくいく

プロジェクトリーダーが損失回避思考をやめるだけで、プロジェクトが成功する確率はかなり上がります。
開発中のさまざまなトラブルに対して、早期対応が可能になるからです。
損失回避思考の場合は様子見を選択しがちになるので、問題を早く見つけても対応が後手にまわってしまうことが多いのです。
ぜひ気をつけてみてくださいね。
損失回避思考についてより詳しく知りたい方は
損失回避思考についてより詳しく知りたい方は、「プロスペクト理論」や「行動経済学」について調べてみましょう。
システム開発でこういう話をしている人はあまりいないので、IT関係の情報を調べてもほとんど出てきませんのでご注意ください。
損失回避性は「プロスペクト理論」で提唱される心理現象の一つで、プロスぺクト理論は「行動経済学」に含まれます。